8月中旬から目立つようになって来たコバエですが、その後、9月中旬に入ってから数が減っていきます。
その一方で、密かに発生していた生物がいたことに気がつきます。
ついに出ましたミズアブです。。。
ミミズコンポスト零号基内の生物変化(ミズアブの台頭)
9月中旬に入り、ミミズコンポスト零号基へいつものように生ゴミを投入し、攪拌させていたときです。見慣れない大きめの幼虫を複数発見しました。(群れの写真はきつい方もいると思いますので、スコップの先端側に1匹。。。)

その姿を一目見て確信。ミズアブの幼虫です。
暑い日が続いた8月はミミズがプランター内深部に潜っている間に、8月中旬よりコバエの幼虫が台頭、その後、9月中旬の少しづつ気温が下がり始めてからはミズアブの幼虫が台頭してきたようです。
10月21日現在、涼しくなってミミズも表層に多く見られるようになりましたが、ミズアブの幼虫は、なお健在で、両者入り乱れるようになりました。
一方で、ミズアブと拮抗しているのかコバエはほとんど見られなくなりました。
ミズアブ発生の原因と問題
ミズアブの発生原因
ミズアブ発生の原因として考えられる要因は、コバエ同様に次の3点です。
考えられるミズアブ発生の主な要因 ①ミミズの夏バテ ②生ゴミの内容変化 ③生ゴミの量
まずは、夏バテでミミズの食事量が減ったこと。次に夏場はフルーツなどの水気があり香りの強い甘い系の生ゴミが増えたことですが、そこに、処理能力を超えた生ゴミを与えていたことが一番の原因だと考えています。

そうです。生ゴミの投入量の問題です。
投入量を適切に調節しているベランダのミミズコンポストでは見られていないことからも、ミミズの処理能力を超えた餌(生ゴミ)があるからこそ、他の種が台頭してきたのだと考えています。
ミズアブ発生の問題点
ミミズコンポスト内でのミズアブの問点としては、次の様なことが起こりうるようです。
ミズアブ発生に伴う問題点 ①ミミズが姿をみせなくなる ②生ゴミが減らなくなる ③ミズアブの糞質が悪い(液状化)
現状としては、ミミズも表層まで上がってきており、生ゴミも今までに無いスピードで減っています。むしろミズアブの食欲が旺盛なのではないかという印象です。
糞の質が分からないところですが、今のところ底部の土に変わりは無いように感じています。
零号基内でのミズアブの特徴
9月中旬に入り、いきなり増えてきた感じでした。1ヶ月が経過しましたが、現状としては、数の変動は無く、ミミズと混在しんがら一定の数が見られます。
フタを空けたら成虫が「ぶわ~」ということはありません。今のところ成虫を見たことがなく、幼虫のみです。この後、サナギ化して、成虫の大発生など起きるのでしょうか。。。
基本的には、生ゴミにとりつくように見られ、生ゴミを投入している表層でのみ見られます。
対応について
ミズアブを減らしたいのなら、生ゴミ投入を減らすことが考えられますし、直接採取していく方法や、表層のミズアブがいるところだけを生ゴミごと取り出して天日干して駆除する方法などもあるようです。
初めて見たときは、少し驚きましたが、直ぐに気にならなくなりました(子供以来、虫への体勢が強くなってきているのを感じます)。
ということで、これも様子見で、どのように変化するのか観察します。
嬉しい経験
ミズアブ発生は、見た目にも出来れば避けたい気持ちもありますが、一方で、興味を持って今の状況を楽しんでいます。
ミズアブは、食糧問題の解決策として注目されている品種の一つのようです。
高タンパク質で、栄養価が高く、魚粉に変わる餌料原料への代替え品としても注目され研究されています。
参考資料① 令和4年10月には国立研究開発法人水産研究・教育機構から『配合飼料の魚粉1/2を昆虫粉に替えてもマダイは高成長』という興味深い記事が上がっていました。
参考資料② 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(JIRCAS)でも養殖餌料としての研究が行われています。
養殖業界にいたMauerとしては、養殖ビジネスにおける一番の問題は、この餌料原料の問題だとも考えています。
Mauerの養殖における餌料問題について触れた記事
ミミズコンポストなど、家庭で小さくやっている分には、勝手に増えて困ってしまうミズアブなどのミミズ以外の生物ですが、これを単体でいざ安定的に増やそうと思うと難しいものです。
どういった環境で増え、そして減るのか、その生活史を観察出来る好機と考えれば、今の現状を楽しめてしまうところです。
Mauerが大きな魚をいま育てていたのなら、是非とも餌として与えたいところでした。。。



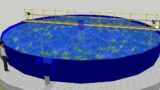


コメント