リチャード・ドーキンス
「生物=生存機械論」
利己的な遺伝子
紀伊國屋書店(1991)
[訳]日高敏隆、岸由二、羽田節子、垂水雄二
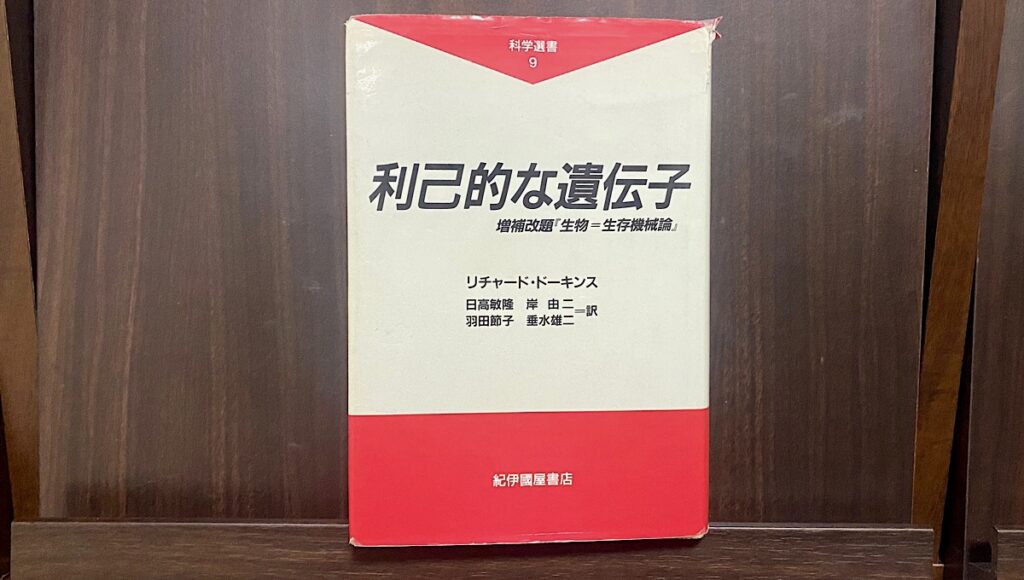
18か19歳頃、恩師の紹介により出会ったのが本書でした。当時は読書習慣もなく、随分と読了に時間を要したのを覚えています。しかしながら、この出会いは画期的で、生命観が180℃変わり、その後の人生観においても大いに影響を受けたベスト5に入る一冊となります。また、読書好きになったきっかけ的一冊でもあり、中々思い入れも強い書籍となっています(笑)。
概要
生物=遺伝子の乗り物
われわれは生存機械―――遺伝子という名の利己的な分子を保存すべく盲目的にプログラムされたロボット機械なのだ。
本書4P「1976年版へのまえがき」
チャールズ・ダーウィンの提唱した進化論において、生物は自然選択が働くことによって、環境に適応し進化すると考えます。
自然選択(自然淘汰)=生存や生殖の優劣、環境の許容量を超えた個体数増加時に働く淘汰圧 環境適応=環境に適した姿形に変化する
一方、この自然選択が働くのは、種、群、個体間など、どのレベルで起きているのかについては、議論が分かれていました。その中で、本書は、遺伝子を起点とした自然選択を提唱します。
遺伝子を起点することで、種や群、個体間における競争関係に見られる利己的な行動だけではなく、一見矛盾する協力関係や自己犠牲による利他的な行動ついても、結果的には遺伝子の利益(自己複製による保存や増殖)に帰結することを見ることが出来ます。あたかも、遺伝子が蔓延ることを最優先にした”利己的な”目的のために、生物が働かされているように見えるのです。
しかしながら”利己的な”とは、あくまでも比喩的な表現です。利他(自己より他者を優先した行動)や対義語としての利己(自己を優先した行動)を使うと少なからず道徳的な意味合いが含まれているように思われますが、遺伝子そのものに意志や目的があるわけではないのです。
遺伝子(DNA)とは、細胞一つ一つの核内に収納された生物の設計図であることが分かっています。また、設計図として身体を構築するための情報を蓄積しつつ、コピーによって同じものを複製できる機能を有します。その振舞には、何者の目的や意志も必要とすることなく、あくまでも物理、化学的な作用により成り立つ原理が働いているに過ぎません。
ダーウィンの「最適者生存」は、じつは安定なものの生存というさらに一般的な法則の特殊な例である。世界は安定したもので占められている。安定したものは、名をつけうるくらいに永続的か、あるいは一般的な原子集団である。
――――地球上に生物が生まれる以前に、分子の初歩的な進化が物理や化学の普通のプロセスによって起こりえたという点である。設計とか目的とか指示を考える必要はない。エネルギーのある所で一群の原子が安定なパターンになれば、それはそのままとどまろうとするであろう。最初の型の自然淘汰は、単に安定したものを選択し、不安定なものを排除することであった。
本書P31—33「2 自己複製子」
遺伝子の構造自体に介入者としての「神」などの存在が働いている可能性はないのか?と思い至ることもできますが、原理的に考えれば、数十億オーダーの時間軸において、物理的、化学的な性質から発生出来る可能性があるのです。
結果、自己犠牲によって他者を助けるような生物個体の利他的で道徳的な行動も、遺伝子が蔓延るための科学的、機械的な反応の先に表現された一つの現象に過ぎないことになります。
――――独立したDNA自己複製子という心躍るイメージを持っている。それは、シャモアのように跳びはねながら、自由奔放に世代から世代へと移り、一時的に使い捨ての生存機械に寄せ集められるものであり、それぞれの個別の永遠の未来に向けて前進しつつ、死すべき生物体を次々と果てしなく脱ぎ捨てていく不滅のコイルである。
本書P374「13 遺伝子の長い腕」
生物とは、遺伝子が永遠を生きるために、自ら作り上げたヴィーグル(乗り物)に過ぎないとして、乗り捨てていく生存機械であると提唱します。
ジーンとミーム
――――どこに住んでいようが、どんな化学的基礎をもって生きていようが、あらゆる生物に必ず妥当するようなものが何かないのだろうか。――――むろん私はその答えなど知らない。しかし、もし何かに賭けなければならないのであれば、私はある基本原理に自分のお金を賭けるだろう。すべての生物は、自己複製子を行う実体の生存率の差に基ずいて進化する、というのがその原理である。自己複製を行う実体としてのわれわれの惑星に威力を張ったのが、たまたま、遺伝子、つまりDNA分子だったというわけだ。
本書P305‐306「11 ミーム 新登場の自己複製子」
生物が発生するための原理が自己複製を行う実体であるのならば、遺伝子(Gene:ジーン)以外の存在があっても良いことになります。ここに、新たな自己複製子として、模倣子(Meme:ミーム)の存在を提唱します。
――――音楽や、思想、標語、衣服の様式、壺の作り方、あるいはアーチの建造法などはいずれもミームの例である。遺伝子が遺伝子プール内で繁殖するに際して、精子や卵子を担体として体から体へと飛び回るのと同様に、ミームがミームプール内で繁殖する際には、広い意味で模倣と呼びうる過程を媒介として脳から脳へと渡り歩くのである。
本書P306‐307「11 ミーム 新登場の自己複製子」
ミームは文化的な要素です。人間だけに見られるものではないのですが、文化的な進化の威力を見せつけることについては、人類は突出しています。
ジーンから生存機械としての生物が誕生することと同様に、ミームからも誕生する生物がありうるのではないかとする刺激的な世界観を広げます。
――――その進化がミームによってもたらされたのかどうか定かではないが、人間には、意識的な先見能力という一つの独自な特性がある。――――遺伝子であれミームであれ、無知な自己複製子というものは、目先の利己的利益を放棄することが長期的には利益につながる場合でも、それを放棄しないのである。――――われわれが例え暗い方の側面に目を向けて、個々の人間は基本的には利己的な存在なのだと仮定しても、われわれの意識的な先見能力――想像力を駆使して将来の自体を先取りする能力――には、盲目の自己複製し達の引き起こす最悪の利己的暴挙から、われわれを救い出す能力があるはずだとうことである。すくなくともわれわれには、単なる目先の利己的利益よりも、むしろ長期的な利己的利益の方を促進させるくらいの知的能力はある。―――われわれは遺伝子機械として組み立てられ、ミーム機会として教化されてきた。しかしわれわれには、これらの創造者にはむかうかう力がある。この地上で、唯一われわれだけが、利己的な自己複製子たちの専制支配に反逆できるのである。
P320-321「11 ミーム 新登場の自己複製子」
自己複製子が利己的であるが故の弱点を補うため、新たな自己複製子としてのミームを進化させることで”先見能力”を作ったとも言えるのかもしれませんが、これが逆に、自己複製子による専制支配への反逆の力になるという視点も刺激的です。
延長された表現型
一つの遺伝子の表現型効果は、通常、それが属する生物体に及ぼす効果のすべてとみなされる。これが従来の定義である。しかしわれわれは今や、一つの遺伝子の表現型効果はそれが世界に及ぼすあらゆる効果として考える必要があると思う。――――私がここで付け加えようとしているのは、この道具が生物個体の体壁の外側まで届きうるということだけである。――――心に思い浮かぶ実例は、ビーバーのダムや、鳥の巣、トビゲラの幼虫の巣といった造作部(構築物)である。
本書P380—381「13 遺伝子の長い腕」
遺伝子が現実に直接の影響を及ぼすことが出来るのは、タンパク質合成だけである。神経系に及ぼす遺伝子の影響は、あるいはついでにいえば、目の色や豆のしわに及ぼす影響も、つねに間接的なものである。遺伝子は、一つのタンパク質のアミノ酸配列を決定し、それがXに影響を及ぼし、それがまたYに影響を及ぼし、それがまたまたZに影響を及ぼし、そして最終的に種子のしわや神経系細胞の配線に影響を及ぼすというわけえある。トビゲラの巣は、こういった因果の系列をさらに先まで伸ばしていたっだけに過ぎない。石の固さは、トビゲラの遺伝子の延長された表現型効果なのである。もし、豆のしわや動物の神経系に影響を及ぼす遺伝子について語ることが正当ならば(すべての遺伝学者はそう考えている)、トビゲラの巣の石の固さに影響を及ぼす遺伝子について語るのもまた正当でなければならい。これはとんでもない考え方ではないか!
本書P384「13 遺伝子の長い腕」
遺伝子が生物の体壁を超えて、影響を与えるという”遺伝子の長い腕”は、カワゲラの巣のように構造物に影響を与えるだけではなく、他の生物の形質にまで影響を与えうることを示唆していきます。
――――遺伝子は、個体の態壁を通り抜けて、外側の世界にある対象を操作する。――――ほんのちょっとの想像力がありさえすれば、放射状に伸びた延長された表現型の力の網の目の中心に位置する遺伝子の姿を見ることができる。世界のなかにある一つの対象物は、多数の生物個体のなかに位置する多数の遺伝子の発する影響力の網の目が集中する焦点なのである。遺伝子の長い腕に、はっきりした境界はない。あらゆる世界には、遠くあるいは近く、遺伝子と表現型効果を繋ぐ因果の矢が縦横に入り乱れている。
本書P425「13 遺伝子の長い腕」
「安定なものの存在」、「自己複製子」という原理の先に、豊かな生命の広がりを見ることが出来ます。生命観を構築する上で、非常に重要なテーマを与えくれる図書です。
本書の魅力
自己複製子という本質的概念
”自己複製子”というキーワードは、本書の核心です。
宇宙のどんな場所であれ生命が生じるために存在しなければならなかった、唯一の実体は、不滅の自己複製子である。
本書P425「13 遺伝子の長い腕」
本書が明らかにしたことは、生命誕生の条件を”不滅の自己複製子”に見出したことです。
これは、Mauer自身の生命観を構築する上でも、本質的で重要な概念になっています。
そして、物理的かつ化学的な諸法則さえあれば、介入者の存在無くして必然的に生物が誕生できることを導くことが出来ます。
Mauerは、神を信仰する宗教家ではありませんが、この概念には、自身の生命観も人生観も覆されたほどの衝撃的なイメージを持ちました。
神なき世界の福音
本書はあくまでも思想や主義、道徳などの主観を離れ、ものごとがどう進化してきたかを淡々と語ることに心がけられています。
しかしながら、一読すれば、本書を離れた所において、新たな問いに向き合いたくなります。一つは、生命や倫理の意味ついて、二つ目は、自己意識や主体性の存在についての問です。
神は無く、生物とはただの無機質な機械と変わらないのか?この世に意味など無いのか?自己とは何か?頭を巡ります。
これらの問いに迫る上でも、本書のキーワードである”自己複製子”は、Mauerに取って、大いなる希望となり、極端に言えば救いでもあると感じました。
なぜならば、例え進化的には意味をなさない概念であったとしても、少なくとも人類において、その生物個体が繁栄するためには利他行動や「愛」が必然的に生まれなければならないことを、証明しているようにも捉えられるからです。
また、その誕生に、”介入者”としての創造主的「神」や、なんらかの形而上学的な存在も必要とせず、無(混沌)から有(秩序)を生み出すことが出来るような世界観に、逆に感動を覚えたのでした。
なお、創造主的「神」がいるかいないかについては、私は「分からない」側の立場にいます。「神」の存在は証明できなければ否定も出来ない存在だからです。しかしながら、仮に「神」が存在していたとしても、戦争、虐殺、など悲劇的な不幸ごとを目に見える形で救済することがない存在であることは、現実的に認識しています。であるならば私にとっての「神」は、いてもいなくても変わらない存在であり、実体としてある目前の大切な人たちを顧みてまで信仰するほどの対象でないと考えている所です。
むしろ、仮に”介入者”が存在したとするならば、”救済”や”祝福”を得られない場合に対して、悲観する以外にないように思えてならないため、むしろ存在しない方が良いと思うほどです。
人生における可能性の自由を、”介入者”を理由にして狭めたくないのかもしれません。。。
人間中心主義や自己責任論的な欺瞞への傾斜には注意が必要ですが、自己複製子から想起するのは、生命そのもには、普遍な意味や倫理などなく、あくまでも生物個体としての人間が、その社会性の中で、自ら意味を見い出し、選択するほかないと言えることです。それは、あらゆる結果を自身の上に帰結させる厳しいものでもありますが、真に自分の行動に責任(主体性)を持つ為の誠実な態度であるように思われます。同時に真に自由であるようにも思われるのです。
そんなMaureは、人生の中で揺れる時、本書を想い出します。もはや逆に聖書(笑)
そして、もう一つの生まれる問いが”自己の存在”です。
その自己意識や主体性といった「心」は、どこから来るのか?ミームの創作物なのか?であるならば、例えばAIに自己意識を持たせることは可能なのか?など。これらについては、本書を越えて横断しなければならないため、ここでは深入りしないようにします。こういった問いの深淵に沈むことが出来る点においても『利己的な遺伝子』は実に刺激的で魅力的な図書なのです。
私の中の長い腕
人工生物圏の構築に駆り立てられること、こうしてブログで情報蓄積に勤しむ行動などは、ジーンまたはミームの長い腕によるものなのか?彼らの囁きが、今の私を動かしているのかもしれないと考えることも、中々楽しく、有意義な時間を与えてくれます。
なお、生命のトリガーたる”自己複製子”への反逆を目論むつもりなど毛頭なく、必要も感じないMauerですが、彼らの繁栄と、その繁栄に生物個体としての利他や「愛」の必要性が保たれるような人生を歩みたいと日々思うところです。
なお、私が読んだ増補版以降、二度ほど大きな改訂を経て、現在最新番として40周年記念版が出ていますね。

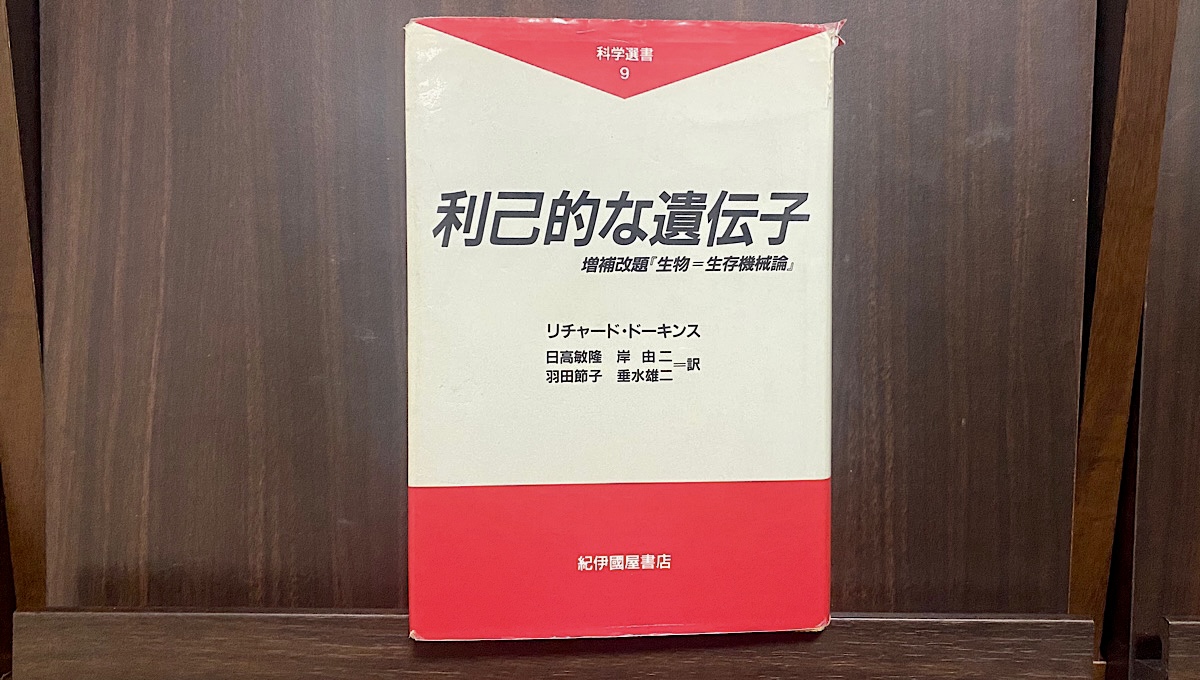



コメント