たなかやすこ
自然の力を借りるから失敗しない
ベランダ寄せ植え菜園
誠文堂新光社(2018)
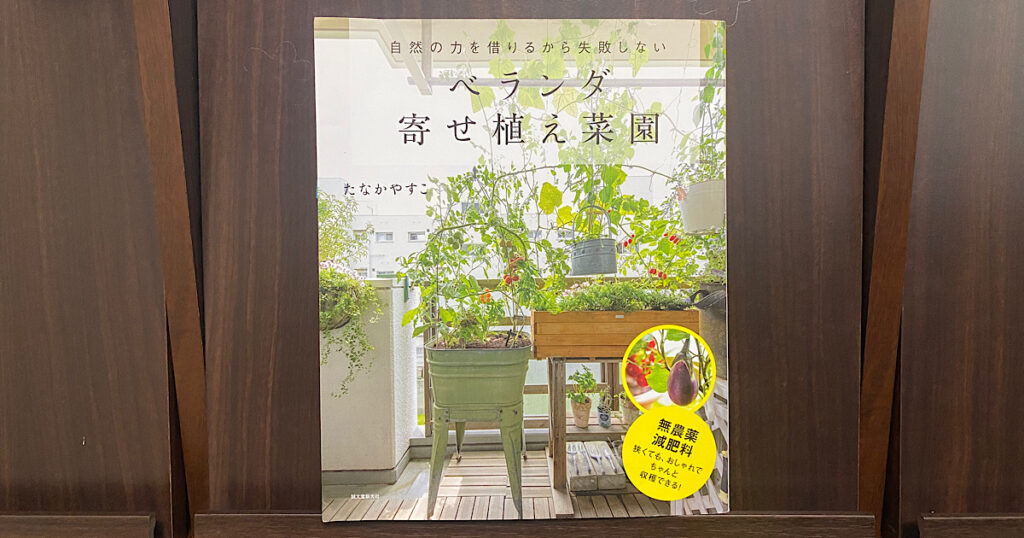
教科書にする
ベランダ菜園を始めるきっかけを作り、人工生物圏構想をMBS(Minimum Biosphere System)として実践に移す為の多くのヒントを与えてくれた、教科書的な大切な図書です。
出会ったのは、上越市直江津に誕生したアジア最大級を謳う無印良品の本棚を散策していた時です。タイトルにある「自然の力を借りる」と「ベランダ寄せ植え菜園」のフレーズに惹かれて思わず手にとったのが本書です。
無換水水槽へ期待することもそうですが、本来、地球にゴミは存在しないはずなのです。
地球誕生約46億年、少なくとも人間の世界が出現してゴミを定義するまでは、ゴミなどというものはなく、生命もまた地球上の同じ材料を使い回して利用し、姿、形、環境は変わっても材料そのものは一度も取り換えられてはいないのです。
だからこそ、人工生物圏をMBSとして構築する上で、水産物を作るのであれば育成水を、農作物も作るのであればその土壌を、使い続けられる方法によって管理しなければならないと考えていました。
本書を手にして最初に導かれたページには、「ぬか床のようにずっと使える土を探して」とあります。ベランダ寄せ植え菜園歴25年の著者による実経験に裏打ちされた理論が、豊富で鮮やかな写真と、著者の優しいイラストとともに説明されていました。
土壌微生物を育てること、ミミズコンポストの活用と、著者の世界に引き込まれ、Rule1の寄せ植えから読み直さなければと、立ち読みをやめて購入しました。
本書では、著者が手掛けた寄せ植えの多様な組み合わせを、品種ごと、季節ごとであったり、同じプランター上で土壌はそのままに、メインの作物が変化しならがら1年中収穫を続けていくさまなども、一気に追うことができます。
ベランダという狭く限られた空間で、こんなにも多様で種類豊かな作物を育てることが出来るのかと驚きを持って眺めることが出来ます。
本書の魅力
また、本書から感じる魅力としては、「一つの豊かなライフスタイルのありかた」というものにも触れられるところにあるのかもしれません。
本書の最終ページの一文は印象的です。
この小さなベランダで育った命にずっと夢中になってきました。
鳥や風が運んできたのか、種が自然に目をだしたり、ミミズの赤ちゃんだって生まれます。
駅からすぐのコンクリートのマンションなのに、桜の頃になるとメジロもやってきます。
そんな自然の循環を身近に感じながら、はっとするような植物の不思議に触れることがあります。
引用元:本処より、『おわりに』142.
ベランダという生活空間に直接的に附属する空間で、形作られる菜園には、著者そのものの感性が存分に表現されているようにも思われます。その空間の生活者自身の気分が上がり、楽しむためには当然といえば当然なのですが、そのことに改めて気づかせてくれました。
前職の関係上、システムを考えるときは、最終的には費用対効果などの目線から見ようとしてしまうところがありました。
例えば、家庭菜園で出来上がる作物は、スーパーなどの末端価格と比べてどうなのか?とか、菜園の管理に掛ける時間や労力をどれだけ省力化できるだろうか?など、そんな思考をしてしまうようなところがありました。
貧しい。
経済性を高めることを否定したいのではありませんし、勿論、著者の作り上げる作物を金銭的に評価したいなどと喚いているわけでもありません。
ただ、著者が紹介する寄せ植えや土作りの理論、工夫したアイデアや使用する道具など、そのモノのストーリーに「愛着」であったり、「優しさ」や「愛情」といったモノを感じることができ、豊かさの一つの答えに出会ったようにも感じたのです。
また、本書の良い所は、形に嵌めたような理論を押し付けない所にもあるのかもしれません。
土作りの基本や寄せ植えの多様な組み合わせはふんだんに掲載されていますが、例えば、品種ごとの詳細な管理方法などについては、触れられていません。
しかし、寄せ植え菜園の全景や、著者の生活空間で生み出された工夫されたスタイルに触れることで、読者自身にもまた、そこから先の物語を自由に歩むことを許してくれるような落ち着いた余裕を見せてくれます。
とにかく、読めば、ベランダ寄せ植え菜園に引き込まれ、初めて見たくなる危険な一冊です(笑)。

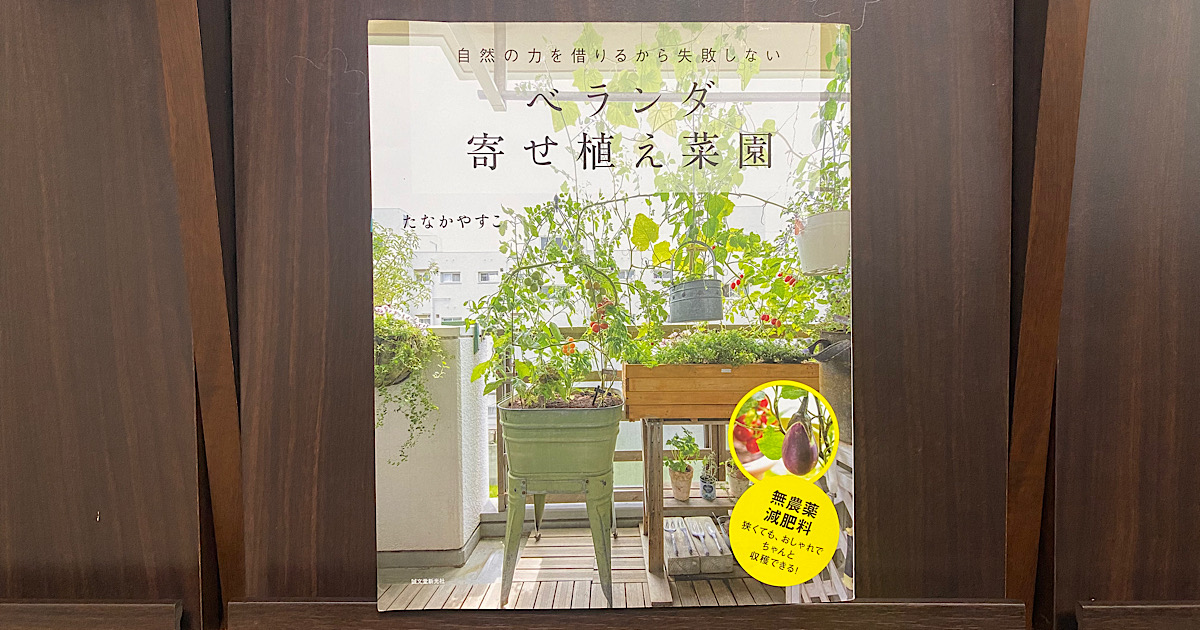



コメント
[…] […]
[…] […]
[…] […]