アビゲイル・アイリング/マーク・ネルソン
バイオスフィア実験生活
史上最大の人工閉鎖生態系での2年間
講談社(1996)
[訳]平田明隆
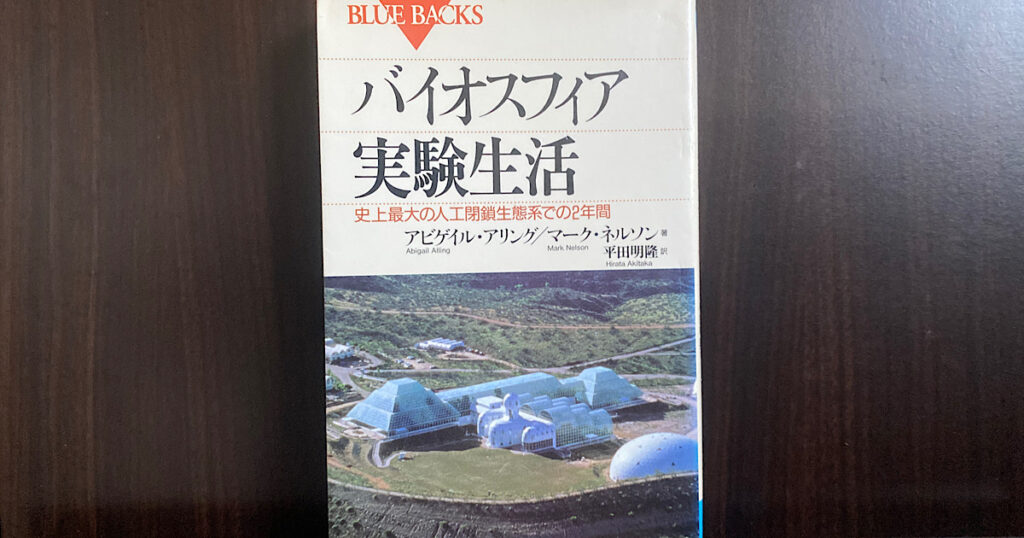
人工生物圏を考える上で、絶対に欠かせない一冊となるのが『バイオスフィア実験生活』です。
バイオスフィア2と本書の概要
地球をバイオスフィア1とし、バイオスフィア2は、ガラス張りの密閉空間に閉じ込めた人工生態系で、その名称は「第2の生物圏」の意です。
バイオスフィア2は、アリゾナの砂漠を舞台に、森林、草地、砂漠、海、湿地、農地そして都市など、地球の生態系を7つに大別、これを1.2haの密閉されたガラスの建物に閉じ込め建造されました。
ここに、男女4名ずつの8名の研究者が1991年9月から93年9月までの2年間をバイオスフィアリアンと自称し、水や食料はもとより、空気さえもリサイクルしながら、外部からの補給なしに共同生活を行ったのです。
プロジェクトの目的としては2点、密閉された空間内での特に物質循環に注目した「地球環境問題の研究」と惑星移住などを想定した「密閉された閉鎖生態系内で人が生存可能なのか検証」を行うことでした。
本書は、バイオスフィア2内で実際に2年間生活した一期目のクルーにより執筆された図書となります。
バイオスフィア2の生態系の管理から、発生した問題。そして、クルー達の生活や心理面について、その実情がありありと語られています。
当初は、2年交代で100年継続させる計画でしたが、経営陣の対立や解任劇の末、メンバーを交代した2期目の途中で中断することになります。
その後は、閉鎖生態系内での長期実験生活は取りやめとなり、研究内容も絞りながら、コロンビア大学、アリゾナ大学へと管理者が変わっていきます。
バイオスフィア2は、地元の資産家からの出資により、約2億ドルもの巨額を投じて運営されました。
しかし、食料不足に伴う1日平均2000カロリー弱の食事、不可解に減少する酸素によりって4000m級の高地と同程度の薄い酸素の中で呼吸するハメになったこと、ゴキブリの爆発的発生など、多くの問題が発生。
完全閉鎖を謳いながらも、外からの酸素の投入や物資支援など、プロジェクトの詰めの甘さも指摘されることになります。
結果、2億ドルもの費用を投じながら、わずか8人の人間が生活するための環境を作り出せなかったとして、科学者やアメリカ本国においては、バイオスフィア2は「失敗」との認識が一般的になってしまったようです。
しかし、本書を一読すれば、少なくとも、バイオスフィア2内部で生活した著者らが経験した課題や問題へのアプローチ、そして心的変化などは、今なお多くの問題を抱えるバイオスフィア1(つまり地球)に暮らす私たちに教訓と考えるヒントを与えてくれることは間違いありません。
また、だからこそ、バイオスフィア2は未だに再考されているのだと思われます。
『COURRIER JAPON』が和訳した2019の『 New York Times News Service』は、比較的新しい記事です。 火星移住を夢見た「世界で最も奇妙な科学実験」は本当に失敗だったのか | 鳥が死に、ゴキブリが繁殖し、極右が現れ… | クーリエ・ジャポン (courrier.jp)
物作りには「失敗」は付きもの。そもそも前例のないプロジェクトです。当時の目標設定や計画、メディア戦略など、様々な問題があったかと思われますが、発生する問題を克服しつつ継続出来ていたのなら、もっと違った結果も生まれたのではないかと思うところです。
本書の魅力
以上を踏まえて、本書の魅力を語るのであれば、私が何よりも外せないのは、”密閉された閉鎖生態系内で2年間も人が生活したその事実”と、”内部で生活したバイオスフィアリアン達の心的変化”です。
本書の重要ポイントとしては、長島氏(2014)の言葉を借りれば、”行為の結果の明示性”にあると考えています。
参考資料:長島美織(2014)『環境リスクと健康リスク:バイオスフィア2の教えること』国際メディア・観光学ジャーナル,19,31-43.
バイオスフィア2内部では、物質循環のスピードがバイオスフィア1の数百倍で廻ります。ゆえに、摂取した水や食事は、体内を通った後に排泄されても、短時間の内に体内に戻ることになります。
つまり、バイオスフィア2内部での何気ない行動も、その行為の結果が、現実的な形でただちで現れることになります。
そして、バイオスフィアリアンは、行為と結果の明示性が、実は存在感や充実感を呼び起こすということを発見します。
著者のバイオスフィアリアンは、修復生態学の先駆者の一人、ビルジョーダンの問いかけに次のように答えます。
「もし、あなたの住む小さな世界の全てが測定出来、物理的性質をみんな知ってしまったとしたら、それでもあなたは何か未知のものを求める気持ちになりますか?[・・・・]。自分の世界に自分自身が責任を持つことになったら、あなたの経験があなたの自由の重荷になって束縛することになりませんか?」
答えはノーである。バイオスフィア2での経験はわれわれに希望を与えた。人間が、自分たちの行為の結果がはっきりわかる世界に住んで、自分たちの存在感を感じとれたのははじめてのことだ。人間が、生命の共同作用の中で積極的な役割を果たし、全システムを健全に保つために必要な一員となり、そこから恩恵を得ることも出来ることがわかったのである。
引用元:本書より、『第10章 三エーカーの”試験管”』241ー242.
こういったバイオスフィアリアンが至った境地をもたらしたモノは何だったのか?また、行為の結果が最も現れるであろう”食を巡る物語”に注目しながら本書を読むのも楽しみです。
また、本書を外れますが、バイオスフィアリアンの一人、ジェーン・ポインターがバイオスフィア2内部での生活についてTEDで語っており、行為と結果の明示性が彼女にあたえた心的変化を垣間見ることが出来ます。
我々はサツマイモをものすごくたくさん食べました。そしてそのサツマイモが私の一部となるのです。[・・・・]。私は文字通り同じ炭素をなんども繰り返し食べていました。ものすごく奇妙な方法で、私は私自身を食べていたのです。
(...バイオスフィア1に戻った後)
以前は私は自分の食べるものを全てを育てていました。しかし今では自分の食べ物に何が入っているか、それがどこからくるか分からなくなりました。それどころか自分が食べているものの名前が半分くらいしか分かりません。店の棚のところで、何時間も 全商品の成分を調べていたりします。頭が変になったと思われているでしょう。本当に驚くべきことです。私は次第に、自分たちが住んでいるこの大きなバイオスフィアの中のどこにいるか分からなくなりました。バイオスフィア2では、私自身がバイオスフィアに対して常に大きな影響を持つこと、 バイオスフィアが私に影響することを理解していました。肉体的にも、また文字通りにも。
引用元:TED日本語 – ジェーン・ポインター: バイオスフィア2での生活 | デジタルキャスト (digitalcast.jp)
“行為と結果の明示性”という視点は、私の考える人口生物圏構築における”「モノ」の評価”に対する考え方の源流として影響を与えました。
なにより、行為と結果の明示性が、物質循環のシステム構築に欠かせないだけでなく、そこで生活する人にとっての存在感や充実感を呼び起こすという点には、意義深いものを感じました。
陸上養殖の循環システムを考えていた頃もそうですが、この循環システムの究極的形態を妄想するとき、その思考は、循環システム内の対象を魚などの水産物から人に置き換えた場合へと行き着くことが良くありました。もちろん人間工場のような無機質で危険な?世界観などではなく、”人間らしい幸福と豊かな生活をおくるために必要な最小限の空間と循環システムとは何か?”という妄想です。
こんな妄想が人工生物圏研究所の原点にもなるわけですが、そんな視点から、本書を眺めた時、実際に循環システムを構築し、その中で人が生活したバイオスフィア2の実績は大いに関心を寄せる実例となります。
なお、バイオスフィア2そのものの工学的なシステムや構造について理解を深める上では、大野・高倉氏(1996)の資料もお勧めです。プロジェクトの問題点などを分かりやすく指摘されています。
参考資料:大野英一・高倉直(1996)『バイオスフィア2―その中から見た実態―』生物環境調節34(4),339-343.
キーブックとしての価値
バイオスフィア2での知見は、バイオスフィア1における自身の行動についても、顧みる切っ掛けを与えてくれます。
また、選ばれた8人のクルーが、自分達の役割を認識しつつも、2年の共同生活を乗り越えた時には、口を聞かないほどまでに関係性が悪化していた者もいたことは、人間そのものの難しさを教えてくれます。
バイオスフィア2の問題というよりも、人間の社会性そのものの問題という分野に突っ込むことになるわけですが、重要なことです。
そもそも、史上初のプロジェクトで、問題だらけだった密閉空間で2年間もストレスを抱えながら生活すれば、無理もないように思うわけですが、例えば、プロジェクトが継続していて、生態系やその管理システムも熟成していた中であればどうだったのでしょうか?
また、一期目のクルーは欧米中心の西洋人です。例えば食文化一つとっても異なる南米やアフリカ、アジアなど他の文化圏の人が入っていればどうだったでしょうか?
人工生態系(人工生物圏)を構築するだけなら、実はそんなに難しい話ではないと考えています。ただし、そこに人を加わえるとなると、途端に話が変わります。それは、人には、社会性や文化、慣習等、人文的な特性があり、人そのものを組み込むからこそ、まさしくバイオスフィア1の人間社会で起こるあらゆる事象・問題が起こり得ることとなり、その作られた環境へ多大な影響を与えることになると考えるからです。
結果、自然的、理化学的な要素を越え、あらゆる分野に跨って課題が生まれると考えられます。しかし、それもまた人工生物圏の魅力だとも考えています。
その原点としても、本書は重要な図書でありキーブックとなっています。
なお、書籍自体は絶版となっているため古本としてしか手に入らなくなりました。

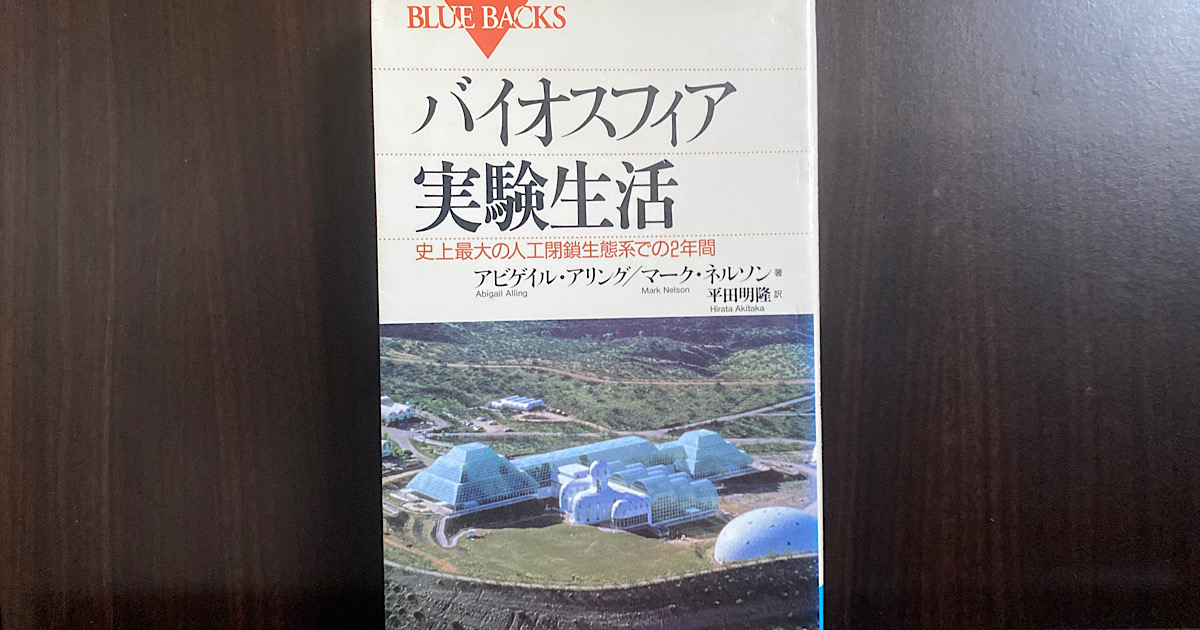



コメント