ベランダ菜園(MBS)とは別ですが、行者ニンニクのプランター栽培を試みています。
昨年から栽培を始め、冬を越して新芽が出ました。その栽培状況についてご紹介します。
行者ニンニクとは?
希少な山菜と知られ、日本では、本州以北から北海まで生息しています。北海道アイヌの言葉では「ブクサ」と呼ばれているようです。葉の形が毒草であるスズランの葉とそっくりであるため採取する際は注意が必要です。
葉は独特な強いニンニク臭を放ち、肉料理と合わせると絶品です。
同種なのか亜種なのか不明ですが、モンゴルで仕事をしていた頃に、現地の家庭料理でしょうゆ漬けされているのを食べたことがあり、この時が行者ニンニクとの初めての出会いでした。
その後、現在の生活拠点である新潟県上越地域の山間にも生息していることを知り、職場の兼業農家H氏より、敷地内に自生する株を分けて頂きました。
種まきしてから収穫できるようになる5~7年の期間を必要とするため、手軽に収穫を楽しむためには株を入手する方が良いですね。
プランターへの植え替え
根を深く張っていくと聞いたので、深底タイプのプランターを用意しました。
また、山菜を育てる場合、自生している土地の土が重要だとの意見も聞いておりましたので、根の周りにつく土は落とさずにプランターへ移しました。足りない分の土はココビートを使用しました。
写真はありませんが、プランターの底から、底砂用の軽石、ココピートベース土です。ココビートベース土と現地の土の比率はおよそ1.5:1でした。
ココビートベース土の配合比(注意:適当配合です) 求めた土壌の性質は、水はけが良く、なるべく粘土化させたくなかったため、ココビートの比率を上げた配合にしてみました。 配合比=ココビート:日向土:富士砂:黒土:腐葉土=10:2:1:1:1 本来は山菜であるため腐葉土を多く使用した方が良いようですが、元々の現地の土壌を十分残しているので、このような配合にしてみました。
もともと半日陰で育ち、直射日光を嫌う植物です。栽培場所は、午前中のみ2~3時間日が当たる半日陰の玄関に配置しました。


2020年6月2日に頂いた時の行者ニンニクの株は、既に花を付けていました。また、株を覆う現地の土には、様々まな雑草から虫類も同居していましたが、取り除くことなくそのままプランターへ植えました。
雑草の主な品種としては、イヌタデ属(多分...)、ドクダミでした。動物は、ミミズ、アリなどです。
現地で元気に成長していた行者ニンニクです。同居する雑草や虫などの動物達と共に最適化された生態系を構築していたはずです。その力を信じて同居させた状態から栽培をスタートさせることにしました。
そもそも、山間に自生していた行者ニンニクを、海抜がほとんどない低地のアパートに運んでの栽培です。このまま栽培を続ければ、栽培環境に合わせた生態系が自動的に調整されるものと考えています。そんな変化を観察出来たら面白いと考えている所です。
栽培状況
収穫と雑草
プランターへ植え替えた後、落ち着いたのを確認して葉を少し残して収穫しました(この収穫方法は間違いで、本当は株ごとに下端を残さなければなりませんでした)。来年も収穫したい場合は、下葉を残しながら収穫しなければならないようですが、この時少し取りすぎていました。
写真は、頂き物と合わせているため実際は、この1/3程度の収穫です。

その後、行者ニンニクは、葉は元気なものの、7月に入ったころには同居しているイヌタデ属が茂り、行者ニンニクが脇役に回っていました。

大いに茂ったイヌタデ属も11月が終わるころには枯れていきました。

12月に入れば雪に埋もれていきました。

冬越し後の成長状況
雪が解けた冬越しの後、3月13日に新芽が出てきているのを確認しました。
写真中央に行者ニンニクの新芽を確認できます。

去年、収穫した際にはほとんど葉を残していなかったため、新芽が出るのか心配でしたが、その後は、順調に成長を続け、4月1日には、行者ニンニクらしい葉を沢山広げてくれました。
花が咲く時期まで葉を残していたため、株に栄養が蓄えられていたのかもしれませんね。

4月18日現在は、そろそろ食べてもよさそうな大きさに成長してきました。

近く子供と収穫して食べようと考えています。
追肥について
今のところまだ追肥はしていません。
経験則でしょうが、山菜を育ているときは下手に肥料はしない方が良いと聞きます。そもそも山菜自体が自然に自生して育っている植物です。
しかしなが、収穫することで、土壌の栄養素は確実に減少していくはずです。
収穫後、減った分を補う意味で自作できたミミズ堆肥を追肥したいと考えています。
おわりに
そもそも、高地にいた行者ニンニクを低地のそれも海よりの地域で本当に育つのか不安がありましたが、今回無事に新芽を出し、順調に成長してくれました。
収穫後、出来れば株分けをしてベランダ菜園の方にも加えられないかと考えている所です。


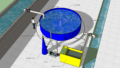
コメント