ミミズコンポストを取り入れて早くも5ヶ月が経過しようとしています。
ここでは、ミミズコンポストの餌場に現れた招かれざる?客(虫)の種類と実施した対策について紹介します。
なお、生ゴミを投入する餌場は、プラ鉢を改造したもので、鉢専用の受け皿を蓋にしています。鉢の構造上、餌を入れすぎなければ蓋はピッタリと閉まり、中型、大型の昆虫は侵入できない構造になっています。

また、和陶器の素焼き風プラ鉢となっているため、表面にザラつきがあります。そのため、蓋をした状態でも密閉状態にはならず、餌場内の蒸れ軽減に一役かっているのではないかと考えていますが、小虫の侵入経路にもなっていそうな構造です。
招かれざる客~発生した虫の種類~
トビムシ類
特徴:体長は1mm前後。植物が成育し土壌が発達するところに広く分布、海の沿岸から森林に至るまで見られ、土壌節足動物中では、ダニ類に次いで個体数の多い種です。
食性は雑食性で、主に植物遺体や菌類を食べ、土壌を作り、体が柔らかくて他の土壌生物のエサにもなるため、土壌生態系を支える「大地のプランクトン」と呼ばれるほどの重要種となります。体に羽はありませんが、危険を察知すると腹部の特殊な器官を使って数10cmほどジャンプできます。
発生状況:ミミズコンポストを始めた当初より、目撃した種でした。今のところ体表が白色の種のみを見ます。餌を入れすぎて分解に時間が掛り、カビなどが発生しがちな時に増殖しがちな様子です。

増えたときは、数十~百規模で見られ、ミミコンの蓋の裏に数十匹ついていました。ミミズ以外では、もっとも目につく種です。おそらく、ミミズを頂いた兼業農家K氏の堆肥場から連れてきたのではないかと考えています。
参考資料: ・武田博清(1982)『野外でのトビムシ個体群の生活史』Edaphologi.27号:23-36 ・井上麻里央,今吉真依子(2010)『トビムシの研究』農芸化学@High School.48巻.4号:291-293.
コバエ類
生態:言わずもがなでしょうが、腐った植物や生ゴミに発生し、薄暗くて湿気が多いところを好むようです。ショウジョウバエ、キノコバエからチョウバエまで来訪したと思います。なお、キノコバエであろう灰黒色の種を最も目撃しています。
発生状況:明らかに、ミミズコンポストの餌場に生ゴミ(野菜くず)を入れすぎて、カビが生えるなどの腐らせたであろう時によく見られます。多く発生しても、一つの餌場でせいぜい5、6匹程度(多いのか?)ですので私としては気にならない程度でした。
また、驚いたのは、交尾が背中合わせで尻と尻を連結させているスタイルであるということでした。初めて見たときは、細長い1匹の虫かと思い、似た形状のアザミウマ類なのかと考えたのですが、交尾中のコバエでした。

なお、コバエが発生するときは、トビムシの方が明らかに優占種となっており、そのためかは分かりませんが、幼虫であるウジを見かけたことが未だありません(卵を産んでいない分けはないと考えていますが)。兎に角、餌を入れすぎないことが肝要ですね。
参考資料: ・辻英明(2005)『果物,ハム,および緑茶の残渣に発生したコバエ類に関する観察』ペストロジー 20巻1号:5-9. ・アース製薬『コバエを知る』
ハエトリグモ類
ハエトリグモ類
生態:徘徊姓で歩き回って餌を捕らえる小型のクモです。
発生状況:ミミズの餌場に餌を投入する時に紛れたのか、自ら進んで侵入したのかは不明です。コバエを取りに来ていると思われますので、そのまま見守っています。実際、1匹しか見ていないので、たまたまなんらかの拍子で侵入しただけだと思われます。

実施した対策
土をかぶせる
最もポピュラーな対策の一つのようですが、生ゴミを土が覆うことでコバエなどは劇的に減ります。トビムシも減っています(潜って目立たなくなるだけ?)。実際、匂いも押さえられますし、土が被せた方がミミズも進行しやすいのか分解も早いと感じています。

エサは細かく
これもポピュラーな対策の一つですが、投入する生ゴミをなるべく細かくしていた方が、明らかに分解は早くなり、腐敗が押さえられます。よって、コバエやトビムシの数が押さえられます。
攪拌する
最初は、自然に任せようと入れるだけにしていましたが、混ぜた方が分解は早いですし、カビが繁ような腐敗も押さえられました。また、放置しすぎて、餌場内にまで植物の根が進行し、スペースを占拠されそうなときがありました。今では、餌を入れる際は攪拌するようにしています。なお、攪拌する際に前回投入分の分解状況も確認できるし、ミミズとこんにちはでき、ミミズの健康具合もチェックできます。

木酢液
腐敗が進行しすぎてコバエが増えた時などに、たまに吹きかけています。その効果があるから、コバエなどの発生が押さえられているのかとも思う時がありますが、1ヶ月に1、2回行うか行わないかの程度なので、効果の良否判断は付いていません。
魚にあげる
増えた時に餌場の蓋の裏に沢山ついているトビムシ。これを、水圏プランター内の住人であるタナゴに与えています。

おぉ….魚の餌も作れてなんと循環チック。タナゴはよく食べてくれます。
みまもる♡(←対策ではない)
腐敗が進行してコバエやトビムシが増えても、基本的には見守ることにしています。
生ゴミの状態や分解具合の何らかの理由で、ミミズ以外の生き物達が住み着くということは、これも自然界からの何らかの知らせでもあります。管理状況を確認する上でも良い指標になると考えていますので、増えたら増えたでできる限り見守り、状況の経過を観察するようにしています。
おわりに
ミミズの餌場における来訪者の記録は、ミミズコンポストを初めて訳5ヶ月間(4-8月)の状況です。今後どのようになるのか、新しい来客を発見すれば、記録していきたいと思います。
なお、どんな虫達でも、ベランダ菜園MBSに訪れる者は、共に生きる仲間として、戦うことはあったとしても敵ではないと考え、あえて「害虫」とは呼ばないようにしています。
言葉遊びではありますが、そのように接してみれば、今のところ出会う虫達も、なかなか可愛くなってきます。
魚の餌にもしてもいますが…

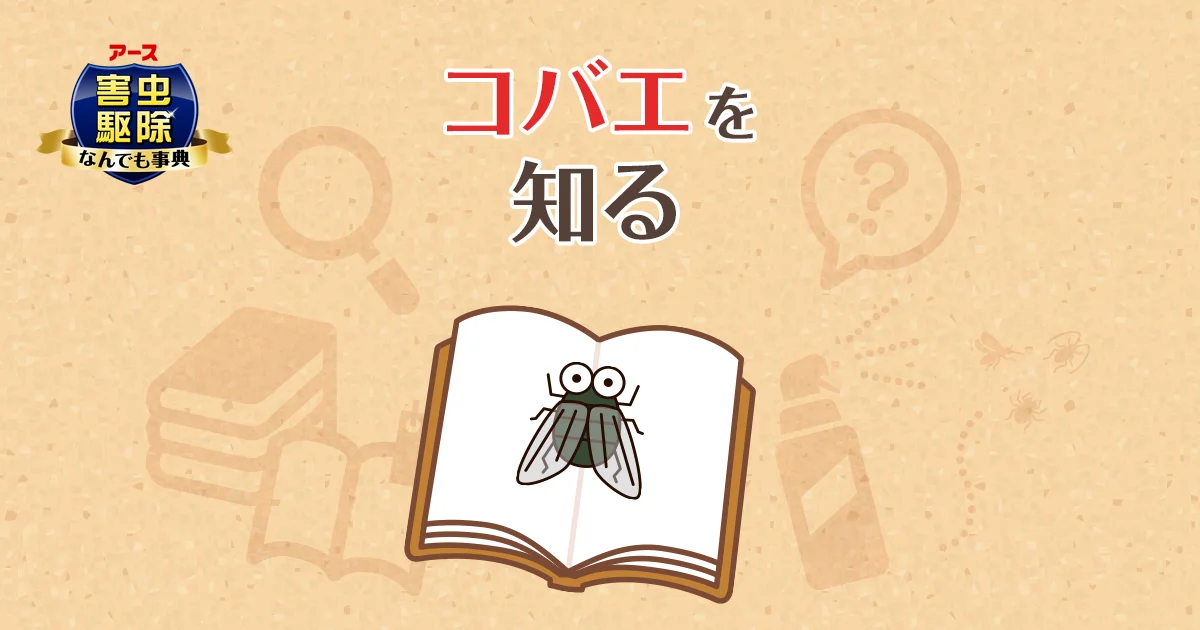


コメント