プランター菜園用に自作したミミズコンポストを紹介していきます。

ここでは、ミミズコンポストに期待できる効果を考えました。
ミミズコンポストに期待すること
土壌生態系を再現するために
当たり前ですが、アパートのベランダには土壌は存在しません。ベランダを中心にした人工生物圏の構築を行う上で、プランター菜園を取り入れました。
プランター菜園において、土作りは最も重要です。
土づくりを考えるうえで、土壌は人が耕すのではなく、根圏をはじめとする土壌生態系の住人に任せ、その生き物たちの力で豊かな土壌を作ってもらいたいと考えています。
その上で、欠かせない重要な生物種の一つになるのがミミズだと考えています。
土壌の栄養素を維持させるために
菜園で育てたものを収穫し、結果的に系外で消費して排泄すれば、どうしても失われてしまう栄養素があります。この不足分の栄養素は、系外から再度持ち込まなければいずれは枯渇してしまいます。
この持ち込まなければならない栄養素としては、家庭で出る生ごみがベストだと考えました。
生ごみをミミズに食べてもらい堆肥にすることでプランターの土壌へ栄養素を補給する。
「生ごみ」を持ち込むメリットとデメリットを、仮説も含めって次のように考えました。
生ごみによる栄養補給のメリット
- 家庭から出される「ゴミ」を「資源」に換えらられる
- 家庭の生ごみは、その家庭の嗜好性を反映するため、結果的にその家庭の嗜好性を反映する菜園の不足した栄養素を補いやすいのではないか
- 分解や発酵が進んでいないフレッシュな食材を菜園に戻すことで、生態系内で進むべき、発酵、分解などの循環の為の段階的な行程を歩ませることができ、菜園内の生態系を豊かにできるのではないか
- 製品としての肥料を購入しないので家計に優しい!
生ごみによる栄養補給のデメリット
- 長年研究されて製品化された「肥料」と比べ、栄養素の不足や偏りが発生する可能性がある
- フレッシュな食材を菜園にもどすことで、害虫や匂いの問題が発生する可能性がある
- 生ゴミとなった素材の素性の把握や適切な処理を行わないと、何らかの薬剤等を菜園に持ち込み生態系を崩す可能性がある
メリットとデメリットを考えた場合、メリットの方が大きいと考え、ミミズコンポストを取り入れることにしました。
デメリットに関しては、長期的に菜園の成長や変化を観察し、工夫によって対処できそうだと考えたからです。
例えば、デメリットの1に関しては、長期的な観察により、特有の症状発見から特定と対処を行うこと。2に関しては、素材の見直しや投入量を調節。3に関しては、素材の来歴や処理方法を見直すと共に生活習慣も見直す(笑
今のところ以上のようなことを考えています。
私としては、メリットの中でも「家庭の嗜好性反映」と「生態系を豊かにする」可能性に着目したいと考えています。
ミミズの驚きの能力
詳しくは、私が教科書とした、たなかやすこ氏の著書をご覧いただきたいですが、注目しているのは以下の効果です。
- 野菜くずなどの生ゴミを食べたミミズの糞が有機肥料としての堆肥となる
- ミミズの糞は無臭で、上手にミミズコンポストを作れば、匂いがしなくなる
- ミミズの糞は窒素、炭素を多く含み、リン酸、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどの成分も植物が吸収しやすい形で含まれている
- 糞の構造は耐水性団粒構造で、水やりをしても崩れにくい
- ミミズの糞が土の中にあると微細な隙間ができ、排水性良くなる
- ミミズの糞は多孔質であるため、水や空気、肥料をため込み、微生物のすみかにもなる
- 糞には、様々なな酵素や菌が含まれ病気の予防になる
- ミミズの腸の中で有機物が消費されるため、植物の近くでも追肥でき根を痛めない
- ミミズが移動することで土が耕され、通過後の隙間は水の通りが良くなる
- ミミズは死ぬと自分の酵素で溶け、土地の養分となる
・・・最高すぎる!
ミミズコンポスト作りが確信に変わりました。
たなかやすこ氏の書籍紹介はこちらで記事にしました。


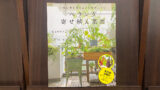


コメント